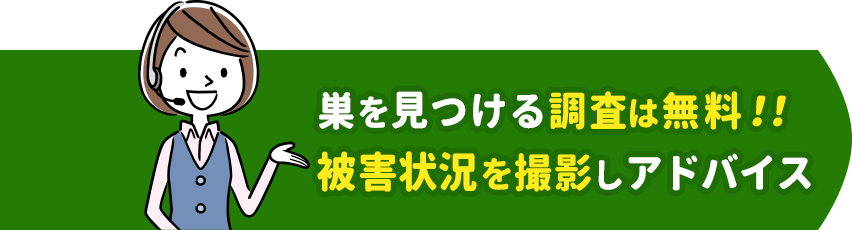ハクビシンを忌避剤で追い出す!オススメの忌避剤や設置方法をご紹介

「ハクビシンの足音が天井から聞こえてくる…」
「糞の匂いが臭すぎる!」
「なんとかして家から追い出したい!」
こんにちは!みんなの害獣駆除屋さんの木村です。
ハクビシンを追い出す方法の一つに、忌避剤を使用する方法があります。
忌避剤とはその名の通り、害獣や害虫が嫌がる匂いや忌避成分が含まれた薬剤。
ハクビシンは鼻がいい動物のため、忌避剤から発生する刺激臭をとても嫌がります。
さらに忌避剤は手軽に設置できるため、自力で対策したい方にはピッタリな方法です。
一方で正しく設置しないとハクビシンの被害が再発し、せっかくの苦労が水の泡なんてことも…。
この記事ではハクビシン対策にオススメな忌避剤や、正しい使い方を詳しくご紹介していきます!
あなたのお悩み解決の手助けになれば幸いです。
それでは参りましょう!
※「すぐにハクビシンの被害から解放されたい!」という方はぜひみんなの害獣駆除屋さんにご相談ください。
地域密着型のみんなの害獣駆除屋さんだからこそ、お電話一本で、最短30分で駆けつけできます!
ハクビシンの弱点は?忌避剤は効果があるの?

ハクビシンは全長90〜110cmほどの、白い鼻筋の模様が特徴的な動物です。
手足の指は5本あり、直径0.8mmのワイヤーの上を渡ることができたデータもあるほど。
電線や木を固定するためのワイヤーの上なども通り道になるんです。
(参考:農研機構 ハクビシンは綱渡りが得意であり、侵入防止経路として配慮が必要である)
またハクビシンは雑食性のため、野菜・果物・昆虫・小動物・人間のゴミをあさって食べます。
繁殖力も高く1年に1回、2〜4匹の子どもを産みます。
生後10ヶ月で繁殖でき、妊娠期間も2ヶ月程度という驚異の短さですので、どんどん増えてしまう可能性もあるんです。
生態については以下の記事で詳しくご説明していますので、ぜひ参考にしてください!
ハクビシンの鳴き声とは?プロが生態や対策法もあわせて徹底解説!
そんなハクビシンの弱点はなんなのでしょうか?
ハクビシンの弱点
ハクビシンの弱点はずばり匂いです。
ハクビシンは嗅覚が非常に発達しており、仲間同士のやり取りを肛門腺から出る分泌物のにおいで行うこともあります。
そのため匂いが強いような次のものを嫌がります。
- ニンニク
- 灯油
- 木酢液
- とうがらしに含まれるカプサイシンなどの刺激成分
- 天敵であるオオカミの匂い
では実際にハクビシンに忌避剤は効くのでしょうか?
ハクビシンに忌避剤は効くのか
先ほどもお伝えした通り、ハクビシンは嗅覚がかなりいい動物です。
忌避剤にはハクビシンの苦手な匂い・成分を使われているため、ハクビシン対策に効果があります!
苦手な匂いを発することでハクビシンを遠ざけ、屋根裏などへの侵入を防ぐことができる効果が期待できるんです。
またすでに侵入していると考えられる場合も、忌避剤を使って追い出せる可能性があります。
この場合、屋根裏などの構造を考慮しつつ追い出すように設置しましょう。
ただ忌避剤は匂いは時間とともに薄まってしまうため、定期的な設置・散布するのが必要になります。
ハクビシン対策にオススメな忌避剤
ではハクビシン対策に使える、オススメの忌避剤をご紹介します!
ご自分でハクビシン対策をしたい方はぜひ参考にしてくださいね。
| 児玉兄弟商会 獣除け線香 | 燻煙タイプの忌避剤 一度の使用で広範囲に対策したい方にオススメ |
|---|---|
| フタワ 強力忌避一番 固形タイプ | 固形タイプの忌避剤 床下や屋根裏での作業が難しい方にオススメ |
| 置くだけ簡単!ハクビシンよグッバイ | 固形タイプの忌避剤 手軽に対策したい方にオススメ |
| 木酢液 | 液体タイプの忌避剤 カンタンに作業したい方にオススメ |
| ウルフピー | 液体タイプの忌避剤 木の枝などにも設置したい方にオススメ |
児玉兄弟商会 獣除け線香
- 主成分:カプサイシン
- 特徴:燻煙タイプの忌避剤
- メリット:部屋中に成分を充満できる
- デメリット:吸引しすぎると人体に有害
- こんな方にオススメ:一度の使用で広範囲に対策したい方
火をつけるとハクビシンが苦手なとうがらしの辛味成分、カプサイシンが含まれた煙が空気中に広がります。
屋根裏や床下など、ハクビシンがよく現れる場所に設置しましょう。
煙が充満するので、部屋のすみ・柱の陰になっている場所にも忌避成分が届きます。
ハクビシンにとっての安全地帯を作らせないことも、この忌避剤のポイントですね。
しかしこの煙は思わず人間も喉に違和感を感じるほど強力です。
リビングなど人やペットがいる空間、風通しの悪い密閉された場所での使用は控えましょう。
フタワ 強力忌避一番 固形タイプ
- 主成分:ハバネロ・木タール
- 特徴:固形タイプの忌避剤
- メリット:手が届きにくい場所にも投げ入れて設置できる
- デメリット:子供やペットが誤食する危険がある
- こんな方にオススメ:床下や屋根裏での作業が難しい方
鼻を突くようなハバネロの刺激臭を発生させる、固形タイプの忌避剤です。
この忌避剤には木タールという成分が含まれています。
木タールはハクビシンにとって山火事を連想させる匂いのため、本能的にその場から離れようとします。
多少ネバ付きのある固形物ですが、ひとつひとつ投げ入れることが可能です。
床下など、入ることが難しい場所にはこちらの忌避剤がオススメですよ。
置くだけ簡単!ハクビシンよグッバイ
- 主成分:カプサイシン
- 特徴:固形タイプの忌避剤
- メリット:脱臭効果や湿度調整の効果もある
- デメリット:子供やペットが誤食する危険がある
- こんな方にオススメ:手軽に対策したい方
こちらの固形タイプの忌避剤は、カプサイシンを使っていることで対策できます。
小袋に入っていますので、手を汚すことなくカンタンに設置可能。
またゼオライトという石を忌避剤として使っています。
この石は脱臭や湿度調整の効果があるため、カビやダニなどの発生を抑えることもできるんです…!
手軽に対策したい方にオススメですよ!
木酢液
- 主成分:木タール
- 特徴:液体タイプの忌避剤
- メリット:吹きかけるだけで簡単に使用できる
- デメリット:雨などによって成分が流されてしまう可能性がある
- こんな方にオススメ:カンタンに作業したい方
木酢液とは木炭を製造する過程で得られる、上澄み液のことです。
先ほどもご紹介した、ハクビシンに山火事を連想させる木タールという成分が主に含まれています。
こちらをスプレーボトルを使ってハクビシンの通り道に吹きかけることで、十分な忌避効果を得ることができます。
ただし雨の影響で成分が流されてしまうこともあるため、屋外で使用する際には十分注意しましょう。
ウルフピー
- 主成分:オオカミの尿
- 特徴:液体タイプの忌避剤
- メリット:専用の小分け容器を使えば、木の枝などにも設置できる
- デメリット:尿の強烈な匂いが周囲に広がってしまう
- こんな方にオススメ:木の枝などにも設置したい方
名前の通り、オオカミの尿を100%含んだ忌避剤です。
使用すると強烈な肉食動物の尿の匂いが広がります。
オオカミはハクビシンにとって天敵のため本能的に逃げ出してしまい、匂い自体に慣れにくいのも特徴です。
付属の小分け容器に入れて使用するため、木の枝などにひっかけて設置することもできますよ。
さてここまで、オススメのハクビシン忌避剤をご紹介してきました。
ご自分に合う忌避剤を選んでみてくださいね!
一方で忌避剤はご自分で作ることも可能です。
ハクビシンは強い匂いが弱点で、売っている忌避剤にもカプサイシンなどが含まれています。
そのためご自分で強い匂いの成分を用意し、忌避剤を作ることもできるんです!
今回はニンニクを使った手作り忌避剤の作り方をご説明しますね。
- ペットボトルに数カ所穴を空ける
- つぶしたニンニクを入れる
- 侵入口から離れたところに設置する
ただニンニクの匂いはゴキブリが好みますので、使う際には注意してくださいね。
では実際にハクビシン対策を行うには、どうすればいいのでしょうか?
これから詳しくご説明しますね。
忌避剤を使ってハクビシンを追い出す方法

ここからは忌避剤を用いて、ハクビシンを追い出す方法を紹介していきます。
ここで一点、注意しておきたいことがあります。
それはハクビシンは『鳥獣保護法』という法律によって、保護されている動物であるという点です。
(参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索)
もちろん追い出すという行為自体は法律違反にはなりません。
ですが、無許可で駆除・捕獲することは禁止されています。
作業中、ハクビシンに遭遇してしまうこともあるかもしれません。
あやまって傷つけてないように十分注意してくださいね。
それではさっそく、ハクビシンを追い出す方法を実際の作業の流れに沿って解説していきます。
- 侵入口や被害状況を確認する
- 忌避剤を設置する
- 侵入防止・掃除を徹底する
詳しくご説明しますね。
①侵入口や被害状況を確認する
まずはじめに侵入口や糞の量といった、以下の3点を確認しておきましょう。
- ハクビシンがどこから侵入しているか
- 巣は作られているか
- 糞や尿の量はどの程度か
ハクビシンがどこから侵入しているか
最も効果の高い位置に忌避剤を設置するために、ハクビシンの侵入口を把握することが大切です。
また再発防止のために侵入口を封鎖する必要もあるため、侵入口の確認は完璧な駆除の第一歩といえるでしょう。
よくあるハクビシンの侵入口は以下の通り。
- もろくなった外壁に開いた穴
- 屋根と壁の間
- 劣化してできた屋根瓦の隙間
- 基礎コンクリートの通風口
- エアコンの通風口
このように、ハクビシンはとても小さな穴からも体をねじり込ませて侵入できる生き物なんです。
直径9センチほどの穴からも侵入できるほどなんですよ。
(参考:ハクビシンは狭い隙間から侵入できる | 農研機構)
どんなに小さな隙間でも、見逃さずに確認することが大切だと覚えておきましょう。
巣は作られているか
ハクビシンの巣には糞や尿が付着していたり、ノミやダニが大量に潜んでいるため、すべて撤去する必要があります。
住み着いたハクビシンは、天井や壁に使われている断熱材を引きはがして巣にすることがあります。
断熱材がボロボロになっていたり、一箇所に集まっていれば巣を作られているサインです。
糞や尿の量はどの程度か
糞や尿の被害がどの程度なのかも確認することで、追い出し後の清掃が必要かも判断できます。
ハクビシンの糞や尿にはたくさんの病原菌が潜んでいますので、確認する時にはマスクや手袋を忘れないようにしてくださいね。
しかしハクビシン駆除の経験がない方に侵入口の見極めなどの作業は、難易度が高いです。
難しい時は無理をせず、プロに無料の現地調査を依頼しましょう。
②忌避剤を設置する
ハクビシンの弱点である嗅覚を忌避剤で刺激して、追い出していきましょう。
先ほどご紹介した忌避剤を設置してくださいね!
また忌避剤を設置する際には、以下の点に注意しましょう。
- 侵入口から遠い位置に忌避剤を設置する
- 定期的に新しいものと交換する
すでにハクビシンが屋根裏の中に潜んでいる場合、侵入口の近くに設置してしまうと、かえって忌避剤を避けて奥に移動してしまいます。
忌避剤を設置する時は、侵入口から離れた位置に設置してくださいね。
また忌避剤の効果は持続性がなく、時間が経つにつれて効果が薄くなってしまいます。
ハクビシンが完全にいなくなるまで、定期的に新しいものに交換し続けましょう。
なお子供を産んでしまうほどに住み着いてしまっている状況だと、忌避剤でも追い出せないことがあります。
子供を守るため、ハクビシンはなかなかその場を離れようとしないんです…。
そうなってしまうと自力での追い出しはなかなか難しいので、一刻も早く害獣駆除の専門家に相談することをおすすめします。
③侵入防止・掃除を徹底する
ハクビシンを追い出すことに成功したら、再発防止のため侵入口を塞ぎましょう。
なおここでの注意点は、ハクビシンが中にいるのに封鎖しないようにすること。
万が一封鎖してしまうと、そのまま中で餓死してしまい、腐った死体からひどい悪臭や虫が発生してしまうんです…。
必ず完全にいなくなったことを確認してから封鎖するようにしてくださいね!
侵入口を封鎖する際には、パンチングメタルと呼ばれる強度の高い金属製の網を使用します。
ネジでしっかりと固定して、ハクビシンの侵入を防ぎましょう。
侵入口の封鎖が完了したら、糞や尿の掃除を欠かさず行ってください。
放置するとアレルギーなどの原因になってしまうため、しっかりと掃除・除菌を行いましょう。
作業時には手袋やマスクを着用してくださいね。
さてここまで、ハクビシンへの対策法をご紹介してきました。
以下の記事でも詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてくださいね。
【ハクビシンを駆除するには?】ご自分でできるオススメの駆除・対策法
「糞の掃除なんてしたくない…」という場合には、ぜひ一度私たちにご相談ください。
ハクビシンによる被害

ハクビシンの被害に気がついたら、すぐに対処をはじめることが大切です。
忌避剤による追い出しはもちろん効果が見込めますが、自力での作業にはどうしても失敗がつきもの。
何度も挑戦することを想定して、早めに行動することが大切です。
さらに時間が経てば経つほど、ハクビシンによる被害はどんどん大きくなっていくんです。
ハクビシンがもたらす被害には、大きく次の3つがあります。
- 建物への被害
- 健康上への被害
- 騒音被害
それぞれについて詳しく紹介していきますね。
建物への被害
ハクビシンは家の中に侵入するとき、通風口を壊したり、小さな隙間を広げて侵入してくることがあります。
また床や壁の断熱材を食いちぎって寝床にするため、実はボロボロになっていた…なんてことも多くあります。
他にも、ハクビシンの「溜めふん」という習性が、家の天井を腐らせる原因になってしまいます。
溜めふんとは同じ場所に糞尿をし続けるハクビシンの習性のこと。
つまりハクビシンが屋根裏をねぐらにしている場合、間違いなく大量の糞や尿が溜まっているんです。
放置すると天井は徐々に腐っていき、最終的には糞尿の重さで天井は落ちてしまいます。
残念ながら、私はここまで放置してしまったケースを何度もみてきました。
決して他人事だとは思わず、早めの駆除を検討してくださいね。
健康上の被害
先ほど紹介したハクビシンの溜めふんという習性によって、家の中には糞や尿が存在しています。
その糞や尿に潜んでいる寄生虫や病原菌を通して、病気にかかってしまうこともあるんです。
さらに、ハクビシンの体表には大量のノミ・ダニが付着しています。
ダニはアレルギーや湿疹の原因にもなり、ノミは人だけではなくペットも被害にあう可能性があるため注意が必要です。
騒音被害
ハクビシンの被害で最も多いのが騒音被害です。
あなたも「ハクビシンの足音がうるさすぎて眠れない!」という悩みを抱えているのではありませんか?
ハクビシンは夜行性のため、私たちが寝る時間に最も活動が活発になるんです。
ドタドタうるさい音と共に、天井からノミやダニが落ちてくる…一刻も早く駆除をして、ぐっすり眠ることができる夜を取り戻したいですよね。
ハクビシン駆除は「みんなの害獣駆除屋さん」にお任せ
ハクビシンの被害を防ぐためにも、対策をはじめ、確実な追い出し・再発防止を行う必要があります。
私たち「みんなの害獣駆除屋さん」は、地域密着型という強みをいかし、最短30分で現場まで駆けつけることが可能です。
そのため被害が拡大する前に駆除・対策ができますよ。
多くのハクビシン被害を解決してきた経験を生かし、調査から捕獲・追い出し、清掃や再発対策まで施工いたします。

現地調査・お見積もりは無料ですので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
※見積もりに工事が必要な場合は有料となります。
▶︎「みんなの害獣駆除屋さん」へのご相談はこちら
まとめ
ここまでハクビシンに使える忌避剤をご紹介してきました。
ハクビシンの追い出しは自力でも行えますが、侵入口の特定や糞尿の掃除など、一般の方ではなかなか難しい作業も必要になってきます。
最も早く・確実な方法は専門業者への依頼です。
まずは現地調査・お見積もりをご依頼ください!
▶︎「みんなの害獣駆除屋さん」へのご相談はこちら
またハクビシンの被害を予防するためには、以下の点を意識しましょう。
- 生ゴミなどのエサになるものや、落ち葉を放置しない
- 庭の果実をそのままにしない
- 木の枝を剪定する
あなたが1日でも早くハクビシンの被害から解放されることを祈っています。
みんなの害獣駆除屋さんの木村でした。
この記事を監修した害獣駆除の専門家
木村まさひろ
ハクビシンによる被害は早めの対処が大切です。忌避剤を使用しても効果がなかったときや、再発対策が難しい場合にはすぐに専門業者に相談・依頼しましょう!
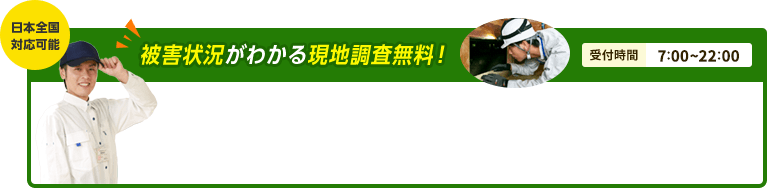
 0120-610-479
0120-610-479
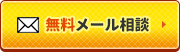
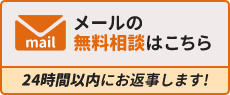

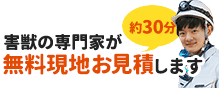
- 被害状況は、写真を見な
がらご説明するから納得! - 駆除は○円、消毒は○円、
と分かりやすく料金を
ご説明します。そして、
必要な作業のみお選び
いただき作業します。
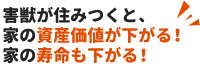

-
■ 屋根裏・床下
フンや食べかすが腐敗し、
天井が抜けたりします。 -
■ 外壁(断熱材)
巣の材料としてちぎられたり、
ダニやノミの巣窟に! -
■ ダニ
10匹のダニは10週間で3千匹、
3千匹のダニは10週間後には
90万匹、と恐ろしいスピード
で増える!
アレルギーや湿疹の原因に。
![]()
- アライグマを駆除するには?害獣被害やすぐできる対策法もご紹介
- アライグマの効果的な対策とは?ご自分でできる対策・撃退法をご紹介
- イタチを自力で駆除するには?駆除法や必要なグッズをプロが解説!
- イタチが来たらどう対策すればいい?生まれる被害や自分でできる対策法
- ハクビシンやタヌキの足跡はどんな形?害獣の足跡の特徴・見分け方
- 害獣による被害に保険は適用される?被害ごとに保険対象かどうかご紹介
- ハクビシンの鳴き声とは?プロが生態や対策法もあわせて徹底解説!
- ハクビシンを忌避剤で追い出す!オススメの忌避剤や設置方法をご紹介
- 【ハクビシンを駆除するには?】ご自分でできるオススメの駆除・対策法
- 【動物のフン】ハクビシンなど害獣のフンの見分け方・起こりうる被害
- 害獣駆除の補助金は何円もらえる?補助金をもらう仕組みや手順をご紹介
![]()